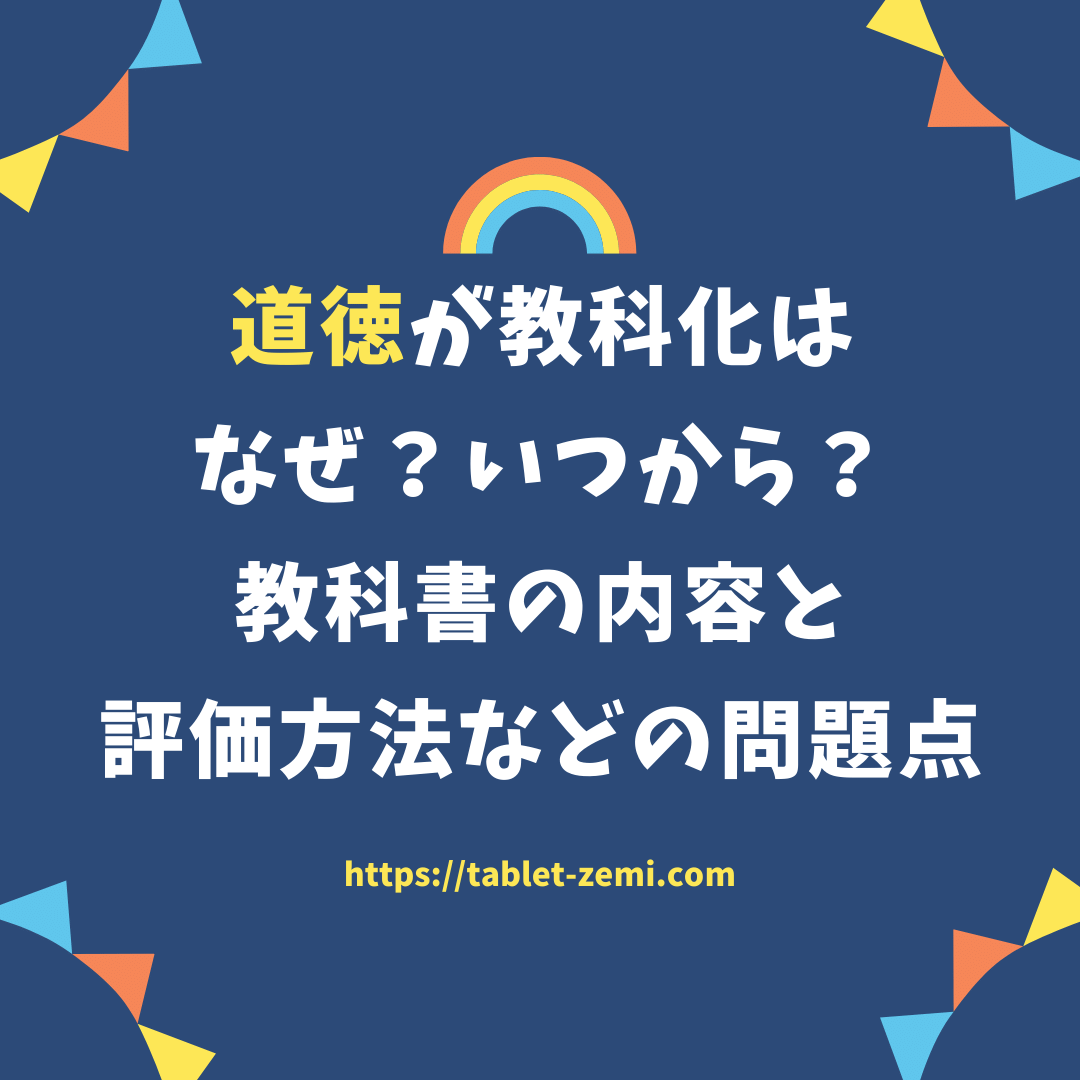
学校の授業として「道徳」を行っていたので意識しなかった人も多いかもしれませんが、今ままでの「道徳」は教科の一つとして行われていたわけではありませんでした。
それが今回、教科の一つとして位置づけられました。
今、どうして道徳の教科化が必要なのでしょうか?
この記事では、
- 道徳が教科化はなぜ?いつから?背景・理由・目的
- 道徳の教科書はどんな内容なのか?どんな特徴があるのか?
- 道徳の教科化の問題点!評価方法などの課題
についてご紹介します。
道徳はなぜ教科化されたのか?
道徳が教科化された理由は大きく分けると2つあります。
一つは子どもたちの心の成長に対する危機感からです。

日本の子どもの自尊感情が低いことは、報道されることも多く知っている人も多いと思いますが、その一方で自分の考えを譲れない自己中心的な考えを持つ子も多く二極化しています。
こうした中で、規範意識や人間関係構築力の低い状況が生まれ、その結果としていじめが起きやすくなっています。
こうした、子どもたちの不安定さを補うために道徳を教科化し、対策しようというのが一つの側面です。
もう一つは、もともと先の状況に先手を打つための道徳なのですが、その昔からある道徳授業が形骸化していることを改めるためということです。
ある意味では
- マニュアル化され
- 先生の思う結論に向かって授業が進む
- 予定調和的な授業
が多くそれが子どもたちの道徳嫌いにつながっていました。
この道徳の授業を、子ども自らが問題意識を持ち、主体的に、そして楽しく学び、好きになるような授業に変えていくために、道徳の教科化をする流れとなったのです。
道徳の教科化はいつから始まるのか?
道徳の教科化は、実は小学校ではすでに始まっています。
小学校では平成30年から全面実施。
中学校では平成31年から全面実施になります。
平成29年3月に学習指導要領の全面改訂が行われたので、この中で道徳の教科化が行われたと勘違いする人もいますが、実際は平成27年に学習指導要領の一部改正が行われており、その中で道徳の教科化が示されたのです。
道徳教科化の目的は
平成27年度に一部改正された小学校学習指導要領の中では、道徳の目標として次のように書かれています。
よりよく生きるための基盤となる道徳性を養うため、道徳的諸価値についての理解を基に、自己を見つめ、物事を多面的・多角的に考え、自己の生き方についての考え方を深める学習を通して、道徳的な判断力、心情、実践意欲と態度を育てる。
これだけでは分かりにくいのですが、内容構成として、
- 自分自身に関すること
- 人との関わりに関すること
- 集団や社会との関わりに関すること
- 生命や自然、崇高なものとの関わりに関すること
の4つの分類の中にそれぞれキーワードが示されています。
例えば、「自分自身に関すること」では、「善悪の判断」「正直・誠実」「節度・節制」などが示されています。
つまり、
- 具体的に学習する内容を示すこと
- 教科書が使用されること
によって、全国的にある一定以上のレベルの道徳の授業を実施することが、この改訂の大きな目的であると思われます。
そして、これらの具体的にされた価値観を「教える」こと以上に、一人ひとりの価値観を「育む」ことが大切にされてきます。
平成29年度3月に学習指導要領の全面改訂が行われ、その中で「主体的・対話的で深い学び」いわゆるアクティブラーニングがキーワードになっています。
その直前に教科化された道徳は、アクティブラーニング型の授業が期待されています。
小学校で英語教科が必修化!新学習指導要綱で授業や入試内容はどう変わる?大学入試も変化する
今の社会状況は、グローバル化の進展や情報通信技術の進歩、少子高齢化の進行といった先の読めないものになっています。

そのため、自ら感じ、考え、他者と対話しながらよりよい方向を目指す力が求められています。
その基盤としての道徳的価値観を育むために、道徳教育が果たす役割は大きいものです。
特に、あらたに教科化された「道徳」は、今までのイメージとは異なる真に学びのある時間に変わっていく必要が求められています。
教科化されたことにより、授業時間が確保されましたが、その内容が変わってくるのはこれからの学校と先生方の力にかかっています。
道徳教科書の内容は?購入方法もご紹介【出版社別比較】

https://www.kyoiku-shuppan.co.jp/docs/doutoku/index.htmlより引用
小学校で道徳が教科になったことの一番大きな変化は、教科書を使用することです。
道徳の教科書はどんな内容なのか?どんな特徴があるのか?
各社の教科書を比較してみましょう。
「道徳 きみがいちばんひかるとき」(光村図書)
1時間の授業が分かりやすくなっています。
導入では、キャラクターの会話を通して主体的に学習に取り組めるよう工夫しています。
さらに、教員用の手引きでは、「考えよう」と「つなげよう」の項目がおかれ、子どもたちの考えが深まる発問が用意されています。
学習のまとまりの最後には毎時間の振り返りを記入できるようになっています。
こうして、毎時間記録したことで自分の成長を後から確認できるようになっています。
「小学道徳 生きる力」(日本文教出版)
教科書名には、人間尊重の精神を徹底し、たくましく生きる子どもを育むという理念がこめられています。
教科書は1時間の流れが分かりやすく作られています。
人間尊重につながるものとして、いじめをなくすよう工夫されています。
いじめに関する知的理解はもとより、役割演技に取り組む体験的な学習や、多面的に考えるコラムなど多様な内容が盛り込まれています。
また、別冊の「道徳ノート」がついていて、1年間の成長を記録できます。
「小学道徳 はばたこう明日へ」(教育出版)
いじめの根底には、人とのつながりが希薄であることがあると考え、他者とのつながる資質や能力を育てられるよう工夫しています。
「考え、議論する道徳」への質的転換を図るために教材は厳選されています。
いじめに関しては、発達段階に応じた教材をそろえています。
ほかにも礼儀とマナーに関する内容や、実体験から価値を理解し行動化するモラルスキルトレーニングも取り入れています。
「小学道徳 ゆたかな心」光文書院
導入・展開・終末・発展がストーリーになった構成でスムーズな授業が行えるように作られています。
教科書の初めにオリエンテーションページがあり、どのように学習を進めるかを学べるようになっています。
さらに、学年40点の豊富な教材があり、子どもの実態に合わせて選択できます。
巻末には「学びの足あと」という記録欄があり、一覧になっているので後で振り返ることができます。
「新しい道徳」(東京書籍)
「いじめのない世界へ」といういじめ問題に特化した教材を全学年に配置しています。
これは複数時間でいじめについて考えるものになっています。
3年生以上では、問題解決的な学習に対応した教材が配置されています。
オリエンテーションページや振り返りページで学習に取り組みやすくしています。
「みんなの道徳」(学研教育みらい)
「考え、議論する道徳」に向けて、自ら課題を見つける力の育成に力が入れられています。
そのため、初めに本文があり、そこから課題を考える作りになっています。
また、「いのちの教育」を重視していて、いじめ防止につながる教材を多数そろえています。
巻頭では自分で見つめるページが、巻末には1年間の学びを振り返るページがあります。
1年間の変化をダイレクトに見ることができます。
「かがやけ みらい」(学校図書)
教材文を味わう「読みもの」と発問を軸に学習を進める「活動」の2分冊の教科書になっています。
「読みもの」は教材文のみで自由な授業が行えるようになっています。
「活動」は見開き構成で、発問や書き込み欄があります。
用意された発問で、道徳的価値観への焦点化を図るとともに、「考えよう」と「見つめよう」の2つの発問で流れが良くなります。
教材に関連する特設ページが設けられ、授業の導入や終末、復習など多様な場面で活用できます。
「小学生の道徳 道徳ノート」(廣済堂あかつき)
本冊と別冊ノートの分冊形式をとっています。
「みんなで考え、話し合う」本冊と、「自分を見つめ、考える」別冊ノートです。
別冊ノートのため記述欄も多彩で、授業前や後、導入時や終末時など柔軟に使用できます。
さらに道徳的価値を発達段階に応じた言葉で説明した解説があり、理解を助けます。
「善悪の判断、自律、自由と責任」「親切、思いやり」「生命の尊さ」を重点項目としています。
考え、議論する道徳へ
多くの教科書では、「考え、議論する道徳」へと質的転換を目指す教科化に対応した工夫がされていることと、いじめに対応していることが共通していいます。
このことから、今までの道徳とは異なり、みんなで考えることが重要視される事が分かります。
また、いじめに対して本気で取り組むという強い意志も感じます。
そして、ノートが付属したり記入欄が設けられたりしていることから、自分で「考えること」と「書くこと」を身につけさせる方針が見て取れます。
道徳の教科化の問題点-評価方法など課題も

道徳は、今までは「道徳の時間」と呼ばれ教科ではありませんでしたが、国語や算数などのように教科の一つになりました。
「特別な教科 道徳」と言われていますが、「道徳」と他の教科はどのように違うのか?そしてどのような問題が考えられるのか?
ここでは、道徳の教科化の問題点、評価方法などの課題についてご紹介します。
道徳の教科化の問題点01.道徳の教科は特別

道徳の授業と、国語や算数の授業と同じ部分は、教科書が使われるということです。
今までも、道徳の時間には授業で使われる本が用意され、その本を中心に授業が進められていました。
しかし、これは副読本という扱いでした。
社会や理科で扱う資料集のようなものです。
道徳の教科化では、これが教科書となり、他の教科と同様になります。
そして、教科となったとこで「道徳」にも導入されるのが評価されるということです。
「評価される」という点は、国語や算数と同じですね。
しかし、その評価方法が他の教科とは違います。
通知表では、国語や算数では数値で評価、学校によってA/B/Cで表記されていたり、各教科の項目ごとに○ついているものとついていないものが表示されているだけということもあります。
しかし、それは決められた基準への到達段階を示しているため、表現の仕方はアルファベットとだったり、○印だったりしますが、つまりは数値評価になります。
これが、道徳という教科ではなじまないと考えられ、文章による評価が行われることになりました。
評価は行うが、数値評価ではない点が異なる部分です。
道徳の教科化の問題点02.評価はどう行われるのか?
では、その文章評価はどのように行われるのでしょうか?
それは、「子どもの学習状況や道徳性に関わる成長の様子」を記述することになります。
そのときに大切にされるのは、
- 多面的な見方で子供を見ること
- 個人としての成長を捉えること
- 一場面ではなく長い期間で見取ること
などです。
では、こうした評価を行うためには、先生と子供にとって何が必要になるでしょうか?
先生は、
- 発言や会話
- 作文・感想文
- ノート
- ワークシート
など多量の記録から子どもの変化を読み取ることになります。
評価の方針としては立派なものが示されていますが、これを忠実に実行することは簡単なことではありません。
良い評価が行われるかどうかは、先生が子供を良く見ていかなければならないでしょう。
もう一つ心配されるのは、評価されるということは、入学試験などのために良い評価を取らなければならないということです。
この点に関して方針としては、
- 調査書に記載しないこと
- 合否判定に活用しないこと
が掲示されていて、表面上は「心配は不要」ということになりそうです。
もちろん、実行性のある方針になるか?はこれからです。
先生の見方に偏りがある場合、大きな問題点になるかもしれませんので、これだけは徹底してほしいと思います。
道徳の教科化の問題点03.具体的な授業はどう行われるのか?

道徳が教科化するにあたって目指していることは、量的確保と質的転換があります。
今まで道徳は教科ではなかったので、学校の都合で道徳の時間が削られることがありました。
これが、教科となったことで授業時間の確保が必須となり、量的な確保が可能になりました。
もう一つの、質的転換は「考え、議論する道徳」のための授業改善です。
今までは、国語的に文章を読み解くだけの授業や、形式化されすぎた授業などが多く見られました。
これを、子どもたちの問題意識を出発点とし、子どもたちの考えや議論を中心とした授業に転換するよう求められています。
ただし、このような授業改善には、時間がかかると思われます。
新しい教育のあり方は、先進的な学校での取り組みをもとにした研究会などが行われ、それをもとに実践が積み上げられて普及していくものです。
そう考えると、方針として示された理想的な「道徳」の授業が行われるのは、まだ先のことになる学校のほうが多いでしょう。
道徳は家庭でも育んでいきたい大事なこと
すでに小学校では始まっている道徳ですが、
- 評価方法
- 評価の利用
- 授業の質的転換の難しさ
など、問題点はまだまだ残っています。
- どのような評価が行われるのか?
- そして子どもたちがどのように変化していくのか?
学校任せにせずに、家庭でもしっかりと見ていかなければならない内容だと思います。







